【翻訳練習 (中→日)】「安田記念香港馬応援団」 ― 2007-06-02 23:30:33
香港競馬会のホームページに載っている短文です。
明日東京競馬場で国際G1レースの安田記念が行われ、香港から4頭もの遠征馬が来日しています。
約四十名市民報名參加打氣團,將於明午(6月2日)飛往日本,於週日到東京競馬場為出戰安田紀念賽的四匹香港賽駒打氣。
「安田紀念賽香港名駒打氣團」由康泰旅行社舉辦。該社董事長、現役馬匹「旅遊領隊」及「旅遊專家」馬主黄士心太平紳士也會與團友們一起到現場支持香港代表。市民如此熱心,馬會特地致贈「亞洲一哩挑戰賽」紀念版T恤予所有團友以示贊賞。
約四十名の市民からなる応援団は、明日(6月2日)の午後は日本に飛び、安田記念に参加する4頭の香港馬を応援するため、日曜日は東京競馬場へ向かう。
「安田記念香港名馬応援団」は康泰旅行社が主催したツアーであり、会長で、現役馬「旅遊領隊」(トラベルリーダー)および「旅遊專家」(トラベルコンサルタント)のオーナーでもある黄士心氏も、団員たちと一緒に現場で香港代表に声援を送る予定。市民たちの熱心さに感謝し、競馬会は特別に「アジア・マイルチャレンジ」記念Tシャツを全参加者にプレゼントした。
過去兩年,康泰旅行社均舉辦打氣團前往日本觀賞亞洲一哩挑戰賽尾站安田紀念賽兼替參賽的香港代表打氣,而市民反應非常熱烈。前年6月5日,「精英大師」領放至臨門一歩飲恨,團友們也吶喊至聲嘶力竭;去年6月4日,「牛精福星」直路衝刺凌厲,大勝兩乘半,團友們無不興奮莫名,如癡如醉!
康泰旅行社は過去2年も、アジアマイルチャレンジシリーズ最終戦・安田記念観戦および香港代表応援のための日本ツアーを主催し、市民の反応も非常に熱かった。一昨年6月5日「精英大師」(サイレントウィットネス)が逃げてゴール前に惜しくも一歩及ばなかったが、団員たちは声を枯らして力の限り応援していた。昨年6月4日、「牛精福星」(ブリッシュラック)が直線で鋭く抜け出して2馬身半圧勝すると、団員たちはだれもが我を忘れて興奮した。
今年競逐安田紀念賽 (國際一級賽1600米)的香港賽駒為歴來最多的一次,包括去年獲得此賽季軍的「勝利飛駒」、2006年國泰航空香港一哩錦標冠軍「星運爵士」、本年度亞洲一哩挑戰賽第三站冠軍一哩賽盟主「歩歩穩」以及主席錦標得主「好爸爸」。前三駒均為一級賽冠軍而後駒亦曾勝二級賽,堪稱陣容鼎盛。
毎年的安田紀念賽,東京競馬場都是人山人海。香港名駒打氣團早已預定「專享指定席」座位,可於接近終點的理想位置觀看群駒衝線。
今年安田記念(国際G1、1600メートル)に参加する香港馬は史上最多であり、去年このレースで3着に入った「勝利飛駒」(ジョイフルウィナー)、2006年キャセイ・パシフィック香港マイルの優勝馬「星運爵士」(ザデューク)、本年度アジアマイル・チャレンジシリーズ第3戦優勝のマイル王「歩歩穩」(エイブルワン)、およびチェマンズトロフィーの優勝馬「好爸爸」(グッドババ)を含む。前の3頭はいずれもG1優勝馬、もう1頭もG2を勝って、最強メンバーだと言っても差し支えない。
毎年の安田記念、東京競馬場はいつも黒山の人だかりだが、香港名馬応援団はすでに「専用指定席」を予約済み、理想的なポジションで各馬のゴールシーンを観戦できる。
明日東京競馬場で国際G1レースの安田記念が行われ、香港から4頭もの遠征馬が来日しています。
約四十名市民報名參加打氣團,將於明午(6月2日)飛往日本,於週日到東京競馬場為出戰安田紀念賽的四匹香港賽駒打氣。
「安田紀念賽香港名駒打氣團」由康泰旅行社舉辦。該社董事長、現役馬匹「旅遊領隊」及「旅遊專家」馬主黄士心太平紳士也會與團友們一起到現場支持香港代表。市民如此熱心,馬會特地致贈「亞洲一哩挑戰賽」紀念版T恤予所有團友以示贊賞。
約四十名の市民からなる応援団は、明日(6月2日)の午後は日本に飛び、安田記念に参加する4頭の香港馬を応援するため、日曜日は東京競馬場へ向かう。
「安田記念香港名馬応援団」は康泰旅行社が主催したツアーであり、会長で、現役馬「旅遊領隊」(トラベルリーダー)および「旅遊專家」(トラベルコンサルタント)のオーナーでもある黄士心氏も、団員たちと一緒に現場で香港代表に声援を送る予定。市民たちの熱心さに感謝し、競馬会は特別に「アジア・マイルチャレンジ」記念Tシャツを全参加者にプレゼントした。
過去兩年,康泰旅行社均舉辦打氣團前往日本觀賞亞洲一哩挑戰賽尾站安田紀念賽兼替參賽的香港代表打氣,而市民反應非常熱烈。前年6月5日,「精英大師」領放至臨門一歩飲恨,團友們也吶喊至聲嘶力竭;去年6月4日,「牛精福星」直路衝刺凌厲,大勝兩乘半,團友們無不興奮莫名,如癡如醉!
康泰旅行社は過去2年も、アジアマイルチャレンジシリーズ最終戦・安田記念観戦および香港代表応援のための日本ツアーを主催し、市民の反応も非常に熱かった。一昨年6月5日「精英大師」(サイレントウィットネス)が逃げてゴール前に惜しくも一歩及ばなかったが、団員たちは声を枯らして力の限り応援していた。昨年6月4日、「牛精福星」(ブリッシュラック)が直線で鋭く抜け出して2馬身半圧勝すると、団員たちはだれもが我を忘れて興奮した。
今年競逐安田紀念賽 (國際一級賽1600米)的香港賽駒為歴來最多的一次,包括去年獲得此賽季軍的「勝利飛駒」、2006年國泰航空香港一哩錦標冠軍「星運爵士」、本年度亞洲一哩挑戰賽第三站冠軍一哩賽盟主「歩歩穩」以及主席錦標得主「好爸爸」。前三駒均為一級賽冠軍而後駒亦曾勝二級賽,堪稱陣容鼎盛。
毎年的安田紀念賽,東京競馬場都是人山人海。香港名駒打氣團早已預定「專享指定席」座位,可於接近終點的理想位置觀看群駒衝線。
今年安田記念(国際G1、1600メートル)に参加する香港馬は史上最多であり、去年このレースで3着に入った「勝利飛駒」(ジョイフルウィナー)、2006年キャセイ・パシフィック香港マイルの優勝馬「星運爵士」(ザデューク)、本年度アジアマイル・チャレンジシリーズ第3戦優勝のマイル王「歩歩穩」(エイブルワン)、およびチェマンズトロフィーの優勝馬「好爸爸」(グッドババ)を含む。前の3頭はいずれもG1優勝馬、もう1頭もG2を勝って、最強メンバーだと言っても差し支えない。
毎年の安田記念、東京競馬場はいつも黒山の人だかりだが、香港名馬応援団はすでに「専用指定席」を予約済み、理想的なポジションで各馬のゴールシーンを観戦できる。
【馬関係の本】「馬と人の文化史」J・クラットン=ブロック ― 2007-06-04 23:54:04

.
清水裕次郎訳、桜井清彦氏監訳、東洋書林発行、原書房発売、となっており、原題は「HORSE POWER ~ A history of the horse and donkey in human societies」、直訳すれば、さしずめ「ホース・パワー ~ 人類社会における馬とロバの歴史」となるんでしょうか?
第1部は「野生のウマとロバ」と題し、考古学および生物学から見た野生のウマ、ロバの話です。
第2部は「誇る祖先もなく、子孫を望みもないウマ科動物」と含みのある題名にしていますが、タイトルから推測される通り、ロバと馬を交配させて生まれるラバやヒニーについて書かれた話です。
そして最後の第3部は「家畜化した馬、ロバ、ラバの歴史」ですが、いわばこの本のメインディッシュ、全書の75%ぐらいのページ数を占めています。
馬とロバの最初の家畜化や、車輪による最初の輸送、乗馬などについての推測もおもしろい内容だし、古代エジプト、スキタイとオリエントの馬から、ギリシャ、ローマの騎兵隊、南北アメリカの征服に至る、ヨーロッパ人中心の視点ではあるものの、広く地球各地域の歴史、伝承を取り入れているところもいいです。
文章のほか、貴重な写真や図面もたくさんあって、とても勉強になりました。
第3部の最後の章は「競馬の歴史」となっていますが、一般にこのタイトルから想像されるサラブレッドの3大祖先の話から始まるものではなく、もっと古く、ホメロス時代の戦車競走から筆を運んでいます。
ちなみに、ホメロスが「イーリアス」のなかで書いている、現存最古?の戦車競走の話は、1着から5着までそれぞれ賞品がつき、レースの参加者(御者と馬)に対する予想にも似た前評判の紹介があったり、レース後の妨害に対する抗議とその審議があったりと、現代競馬の多くの要素がすでに含まれているところが、実に興味深い話です。
清水裕次郎訳、桜井清彦氏監訳、東洋書林発行、原書房発売、となっており、原題は「HORSE POWER ~ A history of the horse and donkey in human societies」、直訳すれば、さしずめ「ホース・パワー ~ 人類社会における馬とロバの歴史」となるんでしょうか?
第1部は「野生のウマとロバ」と題し、考古学および生物学から見た野生のウマ、ロバの話です。
第2部は「誇る祖先もなく、子孫を望みもないウマ科動物」と含みのある題名にしていますが、タイトルから推測される通り、ロバと馬を交配させて生まれるラバやヒニーについて書かれた話です。
そして最後の第3部は「家畜化した馬、ロバ、ラバの歴史」ですが、いわばこの本のメインディッシュ、全書の75%ぐらいのページ数を占めています。
馬とロバの最初の家畜化や、車輪による最初の輸送、乗馬などについての推測もおもしろい内容だし、古代エジプト、スキタイとオリエントの馬から、ギリシャ、ローマの騎兵隊、南北アメリカの征服に至る、ヨーロッパ人中心の視点ではあるものの、広く地球各地域の歴史、伝承を取り入れているところもいいです。
文章のほか、貴重な写真や図面もたくさんあって、とても勉強になりました。
第3部の最後の章は「競馬の歴史」となっていますが、一般にこのタイトルから想像されるサラブレッドの3大祖先の話から始まるものではなく、もっと古く、ホメロス時代の戦車競走から筆を運んでいます。
ちなみに、ホメロスが「イーリアス」のなかで書いている、現存最古?の戦車競走の話は、1着から5着までそれぞれ賞品がつき、レースの参加者(御者と馬)に対する予想にも似た前評判の紹介があったり、レース後の妨害に対する抗議とその審議があったりと、現代競馬の多くの要素がすでに含まれているところが、実に興味深い話です。
サクラローレルの思い出とcherry laurel ― 2007-06-05 23:46:36
土曜日のユニコーンステークス、人気のロングプライドが非常に強いレースを見せました。
順調に成長すれば、やがてはダート重賞、G1の常連となりそうな気がします。
父のサクラローレルにとっては、たぶんサクランセンチュリー以来、久々のJRA重賞勝ち馬です。
サクラローレルはレインボークエスト(Rainbow Quest)産の持ち込み、かのナリタブライアンと同期です。
デビューした頃から、比較的に評判は高かったが、3歳(旧4歳)時は球節炎などでクラシックに出走できなく、4歳(旧5歳)春も天皇賞を前に重い骨折を発症するなど、若い頃は故障が多く、出世が遅れていました。
5歳(旧6歳)、長期休養から復帰すると、いきなり絶頂期に入りました。
この年、宝塚記念とJCを回避していますが、天皇賞・春と有馬記念を勝ち、JRA年度代表馬にも選ばれました。
翌年、凱旋門賞挑戦のためにフランスまで行きましたが、前哨戦のレース中にまたも故障し、本番に出走することなく、引退しました。
現役時はそれほど応援していた馬ではなかった、なぜか引退されてしまうと妙に気になる1頭です。結局G1は2勝止まりでしたが、能力はそれ以上に高い、という印象がずっと頭にあります。
サクラローレルの名前は、オーナーの冠号「サクラ」に月桂樹の「ローレル」(Laurel)からなり、「ローレル」は母ローラローラからの連想かも知れませんが、真否は未考です。
さて、知られているように、ローレルは、アポロンとダフネのあの有名な物語に由来し、ギリシャやローマ時代から神聖視された樹木の一つです。
古代オリンピック・ゲームの優勝者に月桂冠を与えるという話を時々聞くが、手元の「英米故事伝説辞典」によると、それは正しくないようです。
すなわち、古代ギリシャ人は、Pythian gamesの優勝者に月桂樹の冠(wreath of laurels)、Olympic gamesの優勝者にはオリーブの冠(wreath of olives)を与えたようです。
ちなみに、Nemean gamesには green parsely、Isthmian gamesには green pineleavesを、その優勝者に与えたそうです。
最後に小咄を1つ。
前記「英米故事伝説辞典」の続き、「英文学風物誌」からの転載によれば、「坊間に 'laurel' の名称で知られている植物は、通例真正の laurel ではなく、一見類似の植物、特に cherry laurel である。」 と出ています。
cherry laurel ですが、
日本語に訳すと、サクラローレルだったりして (^^;)
順調に成長すれば、やがてはダート重賞、G1の常連となりそうな気がします。
父のサクラローレルにとっては、たぶんサクランセンチュリー以来、久々のJRA重賞勝ち馬です。
サクラローレルはレインボークエスト(Rainbow Quest)産の持ち込み、かのナリタブライアンと同期です。
デビューした頃から、比較的に評判は高かったが、3歳(旧4歳)時は球節炎などでクラシックに出走できなく、4歳(旧5歳)春も天皇賞を前に重い骨折を発症するなど、若い頃は故障が多く、出世が遅れていました。
5歳(旧6歳)、長期休養から復帰すると、いきなり絶頂期に入りました。
この年、宝塚記念とJCを回避していますが、天皇賞・春と有馬記念を勝ち、JRA年度代表馬にも選ばれました。
翌年、凱旋門賞挑戦のためにフランスまで行きましたが、前哨戦のレース中にまたも故障し、本番に出走することなく、引退しました。
現役時はそれほど応援していた馬ではなかった、なぜか引退されてしまうと妙に気になる1頭です。結局G1は2勝止まりでしたが、能力はそれ以上に高い、という印象がずっと頭にあります。
サクラローレルの名前は、オーナーの冠号「サクラ」に月桂樹の「ローレル」(Laurel)からなり、「ローレル」は母ローラローラからの連想かも知れませんが、真否は未考です。
さて、知られているように、ローレルは、アポロンとダフネのあの有名な物語に由来し、ギリシャやローマ時代から神聖視された樹木の一つです。
古代オリンピック・ゲームの優勝者に月桂冠を与えるという話を時々聞くが、手元の「英米故事伝説辞典」によると、それは正しくないようです。
すなわち、古代ギリシャ人は、Pythian gamesの優勝者に月桂樹の冠(wreath of laurels)、Olympic gamesの優勝者にはオリーブの冠(wreath of olives)を与えたようです。
ちなみに、Nemean gamesには green parsely、Isthmian gamesには green pineleavesを、その優勝者に与えたそうです。
最後に小咄を1つ。
前記「英米故事伝説辞典」の続き、「英文学風物誌」からの転載によれば、「坊間に 'laurel' の名称で知られている植物は、通例真正の laurel ではなく、一見類似の植物、特に cherry laurel である。」 と出ています。
cherry laurel ですが、
日本語に訳すと、サクラローレルだったりして (^^;)
【現代の通人】 その1、辻まこと ― 2007-06-07 23:45:42

.
通人の歴史は古いです。
遊里にしけこみ、うつつをぬかし、つかの間の憂世を忘れようとしている人たち、そのなかでも特に練達で模範たる名人とも言うべき方であり、人生の達観者を指します。
現代の通人と言えば、まず登場願いたいのが、僕が心から敬愛する、辻まこと氏です。
百人に一人というイワナ釣りの名手、フランス・スキーの達人、ムササビやカモを打ち落とす鉄砲撃ち、ほれぼれするほどのギター弾き、山をこよなく愛する登山家、詩人、作家、そして画家です。
1956年「美術評論」に掲載されている、自筆の「略歴」によれば、1914年の生まれで、中学に入ってから画描きになりたくなり、学校を中退してヨーロッパに行きました。
1ヶ月間リーヴル美術館を見続け、特にドラクロアの作品にショックを受け、とても勝負にならんと、画家をやめるつもりで毎日フラフラしていました。
先輩に説教されて、やむなく日本に帰国した後はペンキ屋、図案屋、化粧品屋、喫茶店など職業を転々し、そのうち竹久不二彦(夢二画伯の次男)などとともに金鉱探しに夢中し出して、東北信越の山々を駆けめぐったそうです。
戦時は新聞記者になって、一家天津に移り住んだが、そのうち考古学にのめり、山東省で発掘しようとしたところ、兵隊に入れられました。戦後よっやくのこと引き揚げ、その後は結局画描きに近いことを職にした、とのこと。
例えば、次の URLにある絵は、「すぎゆくアダモ」という絵本のなかの作品です。
http://www.ricecurry.jp/
しかし絵だけでなく、ユーモアあふれる文章のなかに人生の叡智を味付けしたエッセイの数々こそが、まことに素晴らしいです。
引用すれば長くなるので、ここでは仕方なく割愛しますが。
ところで、辻まことが友人の小林恒雄に本を贈ったとき、表紙の裏側に次の文を書きました:
「理を説き名を論ずることは美学の1つだと思うが、それが生命化するためには、経験の生理でうらうちされていなければ真実を失うだろう。
人を取り除けてなおあとに価値のあるものは、作品を取り除けてなおあとに価値のある人間によって作られるような気がする」
「理を説き名を論ずる」うんぬんは、鉄心和尚の詩文です。
多摩川探検隊の本にも載せてあり、たぶん辻まことが気に入っているもので、実にその理想、志す生き方を表しているような気がします。
理を説き名を論ずること己に十分なり
蒼世は何れの日に塵気を脱せんや
自由は人間の世に在らずして
放曠なるはただ天上の雲に看るのみ
通人の歴史は古いです。
遊里にしけこみ、うつつをぬかし、つかの間の憂世を忘れようとしている人たち、そのなかでも特に練達で模範たる名人とも言うべき方であり、人生の達観者を指します。
現代の通人と言えば、まず登場願いたいのが、僕が心から敬愛する、辻まこと氏です。
百人に一人というイワナ釣りの名手、フランス・スキーの達人、ムササビやカモを打ち落とす鉄砲撃ち、ほれぼれするほどのギター弾き、山をこよなく愛する登山家、詩人、作家、そして画家です。
1956年「美術評論」に掲載されている、自筆の「略歴」によれば、1914年の生まれで、中学に入ってから画描きになりたくなり、学校を中退してヨーロッパに行きました。
1ヶ月間リーヴル美術館を見続け、特にドラクロアの作品にショックを受け、とても勝負にならんと、画家をやめるつもりで毎日フラフラしていました。
先輩に説教されて、やむなく日本に帰国した後はペンキ屋、図案屋、化粧品屋、喫茶店など職業を転々し、そのうち竹久不二彦(夢二画伯の次男)などとともに金鉱探しに夢中し出して、東北信越の山々を駆けめぐったそうです。
戦時は新聞記者になって、一家天津に移り住んだが、そのうち考古学にのめり、山東省で発掘しようとしたところ、兵隊に入れられました。戦後よっやくのこと引き揚げ、その後は結局画描きに近いことを職にした、とのこと。
例えば、次の URLにある絵は、「すぎゆくアダモ」という絵本のなかの作品です。
http://www.ricecurry.jp/
しかし絵だけでなく、ユーモアあふれる文章のなかに人生の叡智を味付けしたエッセイの数々こそが、まことに素晴らしいです。
引用すれば長くなるので、ここでは仕方なく割愛しますが。
ところで、辻まことが友人の小林恒雄に本を贈ったとき、表紙の裏側に次の文を書きました:
「理を説き名を論ずることは美学の1つだと思うが、それが生命化するためには、経験の生理でうらうちされていなければ真実を失うだろう。
人を取り除けてなおあとに価値のあるものは、作品を取り除けてなおあとに価値のある人間によって作られるような気がする」
「理を説き名を論ずる」うんぬんは、鉄心和尚の詩文です。
多摩川探検隊の本にも載せてあり、たぶん辻まことが気に入っているもので、実にその理想、志す生き方を表しているような気がします。
理を説き名を論ずること己に十分なり
蒼世は何れの日に塵気を脱せんや
自由は人間の世に在らずして
放曠なるはただ天上の雲に看るのみ
【素人写真】「親と子」 ― 2007-06-14 01:21:15
カリール・ジブランはいう:
あなたの子供は、あなたの子供ではない。
彼らは、人生そのものの息子であり、娘である。
彼らはあなたを通じてくるが、あなたからくるものではない。
彼らはあなたとともにいるが、あなたに屈しない。
(中略)
あなたがたは弓のようなもの。
その弓からあなたがたの子どもたちは、
生きた矢のように射られて前へ放たれる。
弓と矢がいつまでもくっついては前に進めない、ということでしょうか。

1993年8月 小岩井牧場

2001年11月 小田原

2006年2月 上海
別シリーズの写真が1枚紛れ込まれたので、削除しました。(2007.06.16)
あなたの子供は、あなたの子供ではない。
彼らは、人生そのものの息子であり、娘である。
彼らはあなたを通じてくるが、あなたからくるものではない。
彼らはあなたとともにいるが、あなたに屈しない。
(中略)
あなたがたは弓のようなもの。
その弓からあなたがたの子どもたちは、
生きた矢のように射られて前へ放たれる。
弓と矢がいつまでもくっついては前に進めない、ということでしょうか。
1993年8月 小岩井牧場
2001年11月 小田原
2006年2月 上海
別シリーズの写真が1枚紛れ込まれたので、削除しました。(2007.06.16)
【レース予想】2007マーメイドステークス ― 2007-06-16 11:44:45
比較的に新しい重賞ですが、歴代勝ち馬に錚々たる名前が並びます。
今年の場合、出走メンバーはどう贔屓目で見ても、一段とレベルが落ちるようです。
現役牝馬のレベルが低いわけではなく、その反対、トップクラスが強すぎて、3歳のウオッカも含めて、来週の宝塚記念にまわっています。
となると、このなかで実績で大いばりできそうなのが、阪神ジュベナイルフィリーズを勝っていたショウナンパントルや、オークス、秋華賞とも掲示板にシェルズレイ 、そして去年の勝ち馬ソリッドプラチナムあたりですかね。
ハンデもコスモマーベラス、スプリングドリューより軽く、ここは彼女たちの復活に賭けるのも悪くないと思います。
◎ ソリッドプラチナム
○ ショウナンパントル
▲ シェルズレイ
△ サンレイジャスパー
パドックで最終決断しますが、たぶん ◎-○、◎-▲、◎-△、○-△の馬連4点で運試し、です。
今年の場合、出走メンバーはどう贔屓目で見ても、一段とレベルが落ちるようです。
現役牝馬のレベルが低いわけではなく、その反対、トップクラスが強すぎて、3歳のウオッカも含めて、来週の宝塚記念にまわっています。
となると、このなかで実績で大いばりできそうなのが、阪神ジュベナイルフィリーズを勝っていたショウナンパントルや、オークス、秋華賞とも掲示板にシェルズレイ 、そして去年の勝ち馬ソリッドプラチナムあたりですかね。
ハンデもコスモマーベラス、スプリングドリューより軽く、ここは彼女たちの復活に賭けるのも悪くないと思います。
◎ ソリッドプラチナム
○ ショウナンパントル
▲ シェルズレイ
△ サンレイジャスパー
パドックで最終決断しますが、たぶん ◎-○、◎-▲、◎-△、○-△の馬連4点で運試し、です。
三寸金蓮 ― 2007-06-19 01:05:21
宣和堂さまのブログで、唐代の「酉陽雜俎」に最古のシンデレラ物語が出ている話と、その話をディスカバリーチャンネルが映像化して放送していたことを紹介しています。(http://sengna.com/log/eid999.html)
中国の伝説が童話シンデレラ物語の起源かどうかは別として、コメントで、ガラスの靴で妃を選ぶ段は足の小さい女性がよいとする考えで、纏足の話まで及んだのはおもしろいです。
どうも中近東でのおとぎ話のなかにも類話があるそうです。
「三寸金蓮」という言葉がありますが、「南史」斉の東昏君が蓮の金弁を貼り、妃の人をそのうえに歩かせては「歩々蓮花を生ず」と言って喜ぶ、というふざけた話に起源するようです。
纏足人の小さな脚の写真を見たことがありますが、気持ち悪い感じこそあっても、まったくどこがきれいかを理解できませんでした。
さて、纏足の起源について、台湾におもしろい説があります。
すなわち、殷の妲己は、元々九頭狐狸精からの変化で、脚だけはうまく化けられなかったので、布で脚を包み隠したが、宮中の女がそれを真似て広がったとか。
いうまでもなく、眉唾物で信頼性ゼロですが、おもしろいので、いいとしましょう。
中国の伝説が童話シンデレラ物語の起源かどうかは別として、コメントで、ガラスの靴で妃を選ぶ段は足の小さい女性がよいとする考えで、纏足の話まで及んだのはおもしろいです。
どうも中近東でのおとぎ話のなかにも類話があるそうです。
「三寸金蓮」という言葉がありますが、「南史」斉の東昏君が蓮の金弁を貼り、妃の人をそのうえに歩かせては「歩々蓮花を生ず」と言って喜ぶ、というふざけた話に起源するようです。
纏足人の小さな脚の写真を見たことがありますが、気持ち悪い感じこそあっても、まったくどこがきれいかを理解できませんでした。
さて、纏足の起源について、台湾におもしろい説があります。
すなわち、殷の妲己は、元々九頭狐狸精からの変化で、脚だけはうまく化けられなかったので、布で脚を包み隠したが、宮中の女がそれを真似て広がったとか。
いうまでもなく、眉唾物で信頼性ゼロですが、おもしろいので、いいとしましょう。
【馬関係の本】「天馬駆ける」 (永田雄三、鈴木八郎 共著) ― 2007-06-20 00:00:28
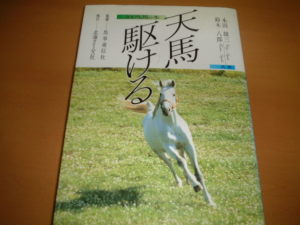
.
このシリーズも、数えれば7回目です。
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/04/11/1394198
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/04/12/1398019
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/04/17/1413570
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/05/12/1501812
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/05/23/1527686
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/06/04/1555875
本の題材をあまり限定していないので、ネタは探せばいっぱいありますが、どちらかというと、そろそろ気力のほうが尽きてきました (^^;)
ちょっと軽めな1冊。
1991年北海道タイムス社より発行されたこの「天馬駆ける」を、僕が本屋で見つけて入手したのは、十年前ぐらいだったと思います。
あるいは、もうちょっと前かも知れませんが。
本書は2つの部からなります。
第1部は「ウマい話にはのろう きみだってウマ通になれる」という、いささかふざけた題名をつけていますが、ほとんど自由気まま、そしてかなりフランクに、いろいろな馬関連の話を、計86篇の短文として綴っています。
「左足と右足どちらが大きい」とか、「ウマ語ってナニ語」とか、「長男と次男どちらが強い」とか、「馬の金の玉」とか、どうでもいいとは言わないが、言わないけれど、ほとんどどうでもいいような話が結構あります。
それがどうして、読んでみると結構おもしろかったりします。
肩凝らずに軽く読めるエッセイとしては楽しいし、案外おもしろいデータや知識もなかに含まれたりします。
第2部「馬と人と」は一転して真面目な伝記ものです。
鎌田三郎、下河辺孫一、吉田善哉、岡田繁幸という、いずれも日本のサラベレッド競馬史に残る、残るであろう4人を、
取り上げています。
社台の吉田さん、ビッグレッド等の岡田さんはともかく、下河辺牧場の創設者について詳しく書いているものを、ほかのところでは読んだことがないので、おもしろく読めました。
ちょっと軽めな1冊だと書いてしまったが、改めて読み直すと、実際はそうではなく、いろいろな素材が積み込まれた、ぎっしりと重みのある書物であります。
このシリーズも、数えれば7回目です。
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/04/11/1394198
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/04/12/1398019
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/04/17/1413570
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/05/12/1501812
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/05/23/1527686
http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/06/04/1555875
本の題材をあまり限定していないので、ネタは探せばいっぱいありますが、どちらかというと、そろそろ気力のほうが尽きてきました (^^;)
ちょっと軽めな1冊。
1991年北海道タイムス社より発行されたこの「天馬駆ける」を、僕が本屋で見つけて入手したのは、十年前ぐらいだったと思います。
あるいは、もうちょっと前かも知れませんが。
本書は2つの部からなります。
第1部は「ウマい話にはのろう きみだってウマ通になれる」という、いささかふざけた題名をつけていますが、ほとんど自由気まま、そしてかなりフランクに、いろいろな馬関連の話を、計86篇の短文として綴っています。
「左足と右足どちらが大きい」とか、「ウマ語ってナニ語」とか、「長男と次男どちらが強い」とか、「馬の金の玉」とか、どうでもいいとは言わないが、言わないけれど、ほとんどどうでもいいような話が結構あります。
それがどうして、読んでみると結構おもしろかったりします。
肩凝らずに軽く読めるエッセイとしては楽しいし、案外おもしろいデータや知識もなかに含まれたりします。
第2部「馬と人と」は一転して真面目な伝記ものです。
鎌田三郎、下河辺孫一、吉田善哉、岡田繁幸という、いずれも日本のサラベレッド競馬史に残る、残るであろう4人を、
取り上げています。
社台の吉田さん、ビッグレッド等の岡田さんはともかく、下河辺牧場の創設者について詳しく書いているものを、ほかのところでは読んだことがないので、おもしろく読めました。
ちょっと軽めな1冊だと書いてしまったが、改めて読み直すと、実際はそうではなく、いろいろな素材が積み込まれた、ぎっしりと重みのある書物であります。
最近のコメント