【レース予想】2008青葉賞 ― 2008-05-02 22:22:44
そもそも勝ち馬が猫の目のように変わる今年の4歳クラシック、そのうえ皐月賞を逃げ切ったキャプテントゥーレが故障で戦線を離脱し、ダービーに向けての勢力地図はますます混迷を極めています。
はっきりとした中心馬が不在なだけに、明日の青葉賞を強い内容で勝ち切る馬が出てくれば、直ちに本番でも人気を集めてしまいそうです。
こんな状況ですから、新たなスターが現れるのを待ち望むのが人情というもので、そこを検討してみましょう。
まず目に付くのは、近年好成績を上げている名門厩舎に所属し、前走武豊騎手を背に、圧倒的な人気で条件戦を勝ち上がって来た馬が3頭います。藤沢和厩舎のクリスタルウイング、松田国厩舎のモンテクリスエス、そして角居厩舎のマゼラン、です。
武豊が選んだためか、3戦2勝のマゼランが前売りでは圧倒的な1番人気になっています。同じく3戦して2連勝中のクリスタルウイングは3番人気、6戦2勝2着3回のモンテクリスエスは人気がありません。
果たして人気ほどの差はあるのでしょうか?むしろキャリアが勝り、堅実さが売り物のモンテクリスエスが、明日では一歩リードすると考えられませんか?
シンボリクリスエスの産駒が大挙4頭も出走して来て、1勝馬のトレノクリスエスを除けば、オリエンタルヨーク、ニシノエモーションとモンテクリスエス、どれもこの距離だと走りそうです。とくにモンテクリスエスは母があのケイウーマン、大型馬ですが、スピードもうまく融合して軽快さが感じられます。
良血と言えばファビラスボーイ。ファビラスラフインの仔でお父さんはダービー馬のジャングルポケット、前走は着差以上の好内容でした。
強敵を相手に走ったスプリングSは5着と、アルカザンも侮れず、新鮮味が薄いですが、勝たれてしまってもまったく不思議ない実力馬です。
毎日杯2着のアドマイヤコマンドは、前売りでは意外と人気がありません。新馬を7馬身差で圧勝したのが売りで、毎日杯では1番人気になっていましたが、新馬戦で下した馬は、どれもその後で勝ち上がっていなく、着差も額面通りで受け取れるか気になります。但し、実は青葉賞では毎日杯から好ステップで、昨年もヒラボクロイヤルが勝っており、抑えておいたほうがいいかも知れません。
◎ モンテクリスエス
○ ファビラスボーイ
▲ アルカザン
△ アドマイヤコマンド
△ マゼラン
△ オリエンタルヨーク、
△ ニシノエモーション
はっきりとした中心馬が不在なだけに、明日の青葉賞を強い内容で勝ち切る馬が出てくれば、直ちに本番でも人気を集めてしまいそうです。
こんな状況ですから、新たなスターが現れるのを待ち望むのが人情というもので、そこを検討してみましょう。
まず目に付くのは、近年好成績を上げている名門厩舎に所属し、前走武豊騎手を背に、圧倒的な人気で条件戦を勝ち上がって来た馬が3頭います。藤沢和厩舎のクリスタルウイング、松田国厩舎のモンテクリスエス、そして角居厩舎のマゼラン、です。
武豊が選んだためか、3戦2勝のマゼランが前売りでは圧倒的な1番人気になっています。同じく3戦して2連勝中のクリスタルウイングは3番人気、6戦2勝2着3回のモンテクリスエスは人気がありません。
果たして人気ほどの差はあるのでしょうか?むしろキャリアが勝り、堅実さが売り物のモンテクリスエスが、明日では一歩リードすると考えられませんか?
シンボリクリスエスの産駒が大挙4頭も出走して来て、1勝馬のトレノクリスエスを除けば、オリエンタルヨーク、ニシノエモーションとモンテクリスエス、どれもこの距離だと走りそうです。とくにモンテクリスエスは母があのケイウーマン、大型馬ですが、スピードもうまく融合して軽快さが感じられます。
良血と言えばファビラスボーイ。ファビラスラフインの仔でお父さんはダービー馬のジャングルポケット、前走は着差以上の好内容でした。
強敵を相手に走ったスプリングSは5着と、アルカザンも侮れず、新鮮味が薄いですが、勝たれてしまってもまったく不思議ない実力馬です。
毎日杯2着のアドマイヤコマンドは、前売りでは意外と人気がありません。新馬を7馬身差で圧勝したのが売りで、毎日杯では1番人気になっていましたが、新馬戦で下した馬は、どれもその後で勝ち上がっていなく、着差も額面通りで受け取れるか気になります。但し、実は青葉賞では毎日杯から好ステップで、昨年もヒラボクロイヤルが勝っており、抑えておいたほうがいいかも知れません。
◎ モンテクリスエス
○ ファビラスボーイ
▲ アルカザン
△ アドマイヤコマンド
△ マゼラン
△ オリエンタルヨーク、
△ ニシノエモーション
【レース予想】2008天皇賞・春 ― 2008-05-04 06:04:22
重賞未勝利のホクトスルタンが、前売りではアサクサキングス、メイショウサムソンのJpnI優勝馬2頭に次ぐ3番人気になっています。
ホクトスルタンが勝てば、メジロアサマ、メジロティターン、メジロマックイーンに続き、4代続けて天皇賞制覇という空前の大偉業が達成されるわけです。
そううまくいくかと思う気持ちがある一方で、どうしても期待したくなるのも、競馬を長く見てきたオールドファンの心情そのものです。
いやいや、本当に可能性はないでしょうか?トウカイトリックはすっかり差し競馬が板に付いたし、アドマイヤメインも前走あたりを見ると、昔ほどむやみやたらと前に行かなくなりました。ホクトスルタンが単騎で逃げて、持ち前のスタミナで粘り込むシーンが浮かんで来ないこともありません。
ポップロックは、凡走しないことで有名です。ここ2年間3着をはずしたのは去年の有馬記念だけで、G1勝ちがまだないですが、たぶんたまたまであって、実力と安定感は現役随一なので、運がまわってくるときもありましょう。
三千メートル以上の長距離G1が2つしか存在日本で、菊花賞馬が天皇賞でいい結果を出しているのは、当然なことです。今年の4歳牡馬、レベルが低いと叫ばれていますが、はたしてアサクサキングスはどうでしょうか?
ダービーを勝つのは運のいい馬、菊花賞を勝つのは強い馬、確かに菊花賞を勝つ当時は頼りなく見える馬も、あとから見れば実は真に強くなった馬ばかりです。スーパークリーク、マンハッタンカフェ、ヒシミラクル...超一流ステイヤーの名が浮かびます。
実績一番なのは無論メイショウサムソンです。前走は見るべきものがなかったのですが、元々叩き良化型で、気力さえ戻れば実績が一番なのは衆目するところです。問題はその気力がどうか、ですが。
◎ ホクトスルタン
○ ポップロック
▲ アサクサキングス
△ メイショウサムソン
△ アドマイヤフジ
ホクトスルタンが勝てば、メジロアサマ、メジロティターン、メジロマックイーンに続き、4代続けて天皇賞制覇という空前の大偉業が達成されるわけです。
そううまくいくかと思う気持ちがある一方で、どうしても期待したくなるのも、競馬を長く見てきたオールドファンの心情そのものです。
いやいや、本当に可能性はないでしょうか?トウカイトリックはすっかり差し競馬が板に付いたし、アドマイヤメインも前走あたりを見ると、昔ほどむやみやたらと前に行かなくなりました。ホクトスルタンが単騎で逃げて、持ち前のスタミナで粘り込むシーンが浮かんで来ないこともありません。
ポップロックは、凡走しないことで有名です。ここ2年間3着をはずしたのは去年の有馬記念だけで、G1勝ちがまだないですが、たぶんたまたまであって、実力と安定感は現役随一なので、運がまわってくるときもありましょう。
三千メートル以上の長距離G1が2つしか存在日本で、菊花賞馬が天皇賞でいい結果を出しているのは、当然なことです。今年の4歳牡馬、レベルが低いと叫ばれていますが、はたしてアサクサキングスはどうでしょうか?
ダービーを勝つのは運のいい馬、菊花賞を勝つのは強い馬、確かに菊花賞を勝つ当時は頼りなく見える馬も、あとから見れば実は真に強くなった馬ばかりです。スーパークリーク、マンハッタンカフェ、ヒシミラクル...超一流ステイヤーの名が浮かびます。
実績一番なのは無論メイショウサムソンです。前走は見るべきものがなかったのですが、元々叩き良化型で、気力さえ戻れば実績が一番なのは衆目するところです。問題はその気力がどうか、ですが。
◎ ホクトスルタン
○ ポップロック
▲ アサクサキングス
△ メイショウサムソン
△ アドマイヤフジ
【馬関係の本】「風の伝説 ~ターフを駆け抜けた栄光と死」(広見直樹) ― 2008-05-05 23:28:24
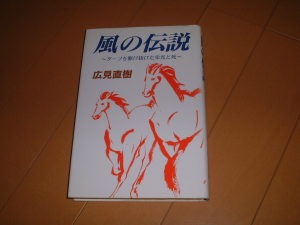
.
図書館より拝借した幸田文の随筆集「雀の手帖」を読んでいると、「尾花栗毛」というタイトルの文章に出会いました。
自然と人情の繋がりを説いた素敵な短文でしたが、「たれこめて灰色の低い空である。風浪立っている海を見おろして、広漠たる無人の秋の放牧場である。まちがいなくあの色の馬が一頭きり、だあっと勇んで鬣もしっぽも振い靡かせて走っていた。ぼけた尾花いろは鉛いろの空の寂しさと、凄い海をおさえてなんと優秀だったか。」のくだりに至るや、ほとんど目の前にその光景が浮かんできて、抑えられないある種の感動を覚えました。
尾花栗毛の馬は、馬群のなかで走っていても、抜けて美しいものです。
その神々しいまでの美しい姿を、初めて僕の目の前に披露したのは、ゴルードシチーだったと思います。
題記の「風の伝説」は、実は同じく先週、図書館に見かけました。
我が家の本棚にも置いてある一冊で、懐かしくなって、久々に引っ張り出して読み直しました。
巻末に、1991年5月18日購入、との筆跡が残っているので、1991年3月26日の発行日からあまり日時を経たずに買っていたようです。(僕には、割と珍しいことです)
この本は、1984年生まれ、1987年のクラシックを賑わった3頭の馬、サクラスターオー、マティリアル、そしてゴールドシチーを取り上げたノーフィクションです。
この世代のダービー馬・メリーナイスや遅れて大成したヒーロー・タマモクロスを含めず、上記の3頭を取り上げていくと、競馬ファンなら先刻承知でしょうが、どうにも悲しい話になってしまいます。
サクラスターオーは皐月賞を勝ったあと怪我をしてしまい、ダービーに出走できず、クラシック最後の菊花賞にもぶっつけで出ることになりました。その久々のレースでなんと奇跡的な勝利を挙げ、杉本清アナに「菊の季節にサクラが満開!」の名文句を吐かせましたが、次の有馬記念ではレース中に再び足を折ってしまい、あっけなく亡くなってしまった名馬です。
マティリアルは、皐月賞前のトライアルで後方からすごい追い込みを決め、競馬ファンの心を捉えて、皐月賞もダービーも1番人気に支持された馬です。ところが、マティリアルはずっと負け続けました。ようやく2年半ぶりの勝星を得たのは1989年のオータムハンデでしたが、そのレース後、ゴールを過ぎた百メートルあたりで、彼も脚を折ってしまいました。手術の甲斐無く、サクラスターオーのあとを追って天国に駆け上りました。
3頭のなか、あの尾花栗毛のゴールドシチーだけは、無事に競走生活を終えました。但し、元々血統的に見るべきものが乏しく、皐月賞と菊花賞の両方でサクラスターオーの2着に入って健闘しましたが、大きなタイトルに届かなかったため、種牡馬にはなれませんでした。馬術の障害馬、もしくは誘導馬を目指して、宮崎競馬場で訓練を受けたとき、やはりひどい骨折から、安楽死処分を受けることに至りました。
この本ではゴールドシチーの骨折を、「自殺」に近いシチュエーションで描いています。その真偽は、作者も言っていますが、むろんわかりません。
但し、いずれにしても、3頭はいずれも妖しい運命のいたずらのなか、劇的で悲運な生涯を送ったサラブレッドだと言えましょう。
悲運の馬は、競馬というスポーツが持つ残酷な一面を映し出す鏡であったり、もっと広く、運命や輪廻そのものの不条理さを語ってくれる存在であったりします。
図書館より拝借した幸田文の随筆集「雀の手帖」を読んでいると、「尾花栗毛」というタイトルの文章に出会いました。
自然と人情の繋がりを説いた素敵な短文でしたが、「たれこめて灰色の低い空である。風浪立っている海を見おろして、広漠たる無人の秋の放牧場である。まちがいなくあの色の馬が一頭きり、だあっと勇んで鬣もしっぽも振い靡かせて走っていた。ぼけた尾花いろは鉛いろの空の寂しさと、凄い海をおさえてなんと優秀だったか。」のくだりに至るや、ほとんど目の前にその光景が浮かんできて、抑えられないある種の感動を覚えました。
尾花栗毛の馬は、馬群のなかで走っていても、抜けて美しいものです。
その神々しいまでの美しい姿を、初めて僕の目の前に披露したのは、ゴルードシチーだったと思います。
題記の「風の伝説」は、実は同じく先週、図書館に見かけました。
我が家の本棚にも置いてある一冊で、懐かしくなって、久々に引っ張り出して読み直しました。
巻末に、1991年5月18日購入、との筆跡が残っているので、1991年3月26日の発行日からあまり日時を経たずに買っていたようです。(僕には、割と珍しいことです)
この本は、1984年生まれ、1987年のクラシックを賑わった3頭の馬、サクラスターオー、マティリアル、そしてゴールドシチーを取り上げたノーフィクションです。
この世代のダービー馬・メリーナイスや遅れて大成したヒーロー・タマモクロスを含めず、上記の3頭を取り上げていくと、競馬ファンなら先刻承知でしょうが、どうにも悲しい話になってしまいます。
サクラスターオーは皐月賞を勝ったあと怪我をしてしまい、ダービーに出走できず、クラシック最後の菊花賞にもぶっつけで出ることになりました。その久々のレースでなんと奇跡的な勝利を挙げ、杉本清アナに「菊の季節にサクラが満開!」の名文句を吐かせましたが、次の有馬記念ではレース中に再び足を折ってしまい、あっけなく亡くなってしまった名馬です。
マティリアルは、皐月賞前のトライアルで後方からすごい追い込みを決め、競馬ファンの心を捉えて、皐月賞もダービーも1番人気に支持された馬です。ところが、マティリアルはずっと負け続けました。ようやく2年半ぶりの勝星を得たのは1989年のオータムハンデでしたが、そのレース後、ゴールを過ぎた百メートルあたりで、彼も脚を折ってしまいました。手術の甲斐無く、サクラスターオーのあとを追って天国に駆け上りました。
3頭のなか、あの尾花栗毛のゴールドシチーだけは、無事に競走生活を終えました。但し、元々血統的に見るべきものが乏しく、皐月賞と菊花賞の両方でサクラスターオーの2着に入って健闘しましたが、大きなタイトルに届かなかったため、種牡馬にはなれませんでした。馬術の障害馬、もしくは誘導馬を目指して、宮崎競馬場で訓練を受けたとき、やはりひどい骨折から、安楽死処分を受けることに至りました。
この本ではゴールドシチーの骨折を、「自殺」に近いシチュエーションで描いています。その真偽は、作者も言っていますが、むろんわかりません。
但し、いずれにしても、3頭はいずれも妖しい運命のいたずらのなか、劇的で悲運な生涯を送ったサラブレッドだと言えましょう。
悲運の馬は、競馬というスポーツが持つ残酷な一面を映し出す鏡であったり、もっと広く、運命や輪廻そのものの不条理さを語ってくれる存在であったりします。
這うものと長いもの ― 2008-05-09 00:42:48
やぶちゃん(http://onibi.cocolog-nifty.com/about.html)のHPを読むと、
Jules Renardはその「博物誌」のなか、Le Serpent(ヘビ)の項
で、"Trop long."(長すぎる)、とただひと事書いているだけ、だそうです。(http://homepage2.nifty.com/onibi/haku.html)
確かに簡潔明快な表現です。
日本でも古来、地方によっては「ナガムシ」と呼んだり、「ナガモノ」と呼んだりします。
この場合、あからさまに呼ぶことを嫌い、うっかり口を出して喚んでしまわないような忌み言葉です。
フランス語の serpent も同じで、語源であるラテン語の serpesは、serpo(這う)の現在分詞だそうです。(「フランスことば事典」、松原秀一、講談社学術文庫)
本来ラテン語でヘビを指す anguis も、古フランス語に入っていたが、ローマ人が直接呼ぶことを避けた結果で、使われなくなったそうです。
英語の snake も、古英語期には snaca と綴られていました。古ドイツ語 snahhan が元になっていると言われていますが、やはり「這う」という意味のようで、おもしろいです。
Jules Renardはその「博物誌」のなか、Le Serpent(ヘビ)の項
で、"Trop long."(長すぎる)、とただひと事書いているだけ、だそうです。(http://homepage2.nifty.com/onibi/haku.html)
確かに簡潔明快な表現です。
日本でも古来、地方によっては「ナガムシ」と呼んだり、「ナガモノ」と呼んだりします。
この場合、あからさまに呼ぶことを嫌い、うっかり口を出して喚んでしまわないような忌み言葉です。
フランス語の serpent も同じで、語源であるラテン語の serpesは、serpo(這う)の現在分詞だそうです。(「フランスことば事典」、松原秀一、講談社学術文庫)
本来ラテン語でヘビを指す anguis も、古フランス語に入っていたが、ローマ人が直接呼ぶことを避けた結果で、使われなくなったそうです。
英語の snake も、古英語期には snaca と綴られていました。古ドイツ語 snahhan が元になっていると言われていますが、やはり「這う」という意味のようで、おもしろいです。
無力な存在 ― 2008-05-16 23:51:23
環境保護に関連して、近年によく聞かれるシナリオでは、人類はほとんど無限の力を持つ天地の主宰、地球は弱く、簡単に割れそうなガラス細工か、すぐにでも破れそうな薄い膜のようなものです。
慎重に、大事に扱わないと、いまにもガラスが割れて、膜が破れそうです。
はたしてそうでしょうか?
他の動物の毛皮でようやく寒さを凌げ、コンクリートで出来た構造物の中に身を隠す人類は、どこにそんなに巨大なパワーがありましょうか?地震、洪水、強風、大自然の猛威の前に、人類は相変わらず無力で、かよわい存在ではありませんか?
数十億年にもなる地球の年齢のなか、人類の仲間が登場したのはせいぜい数百万年前、まして歴史に残る文明時代は数千年です。
長い長い歳月のなか、地球のほうはいくらでも環境の異変を経験してきました、何回もの氷河時代があったし、もしかして巨大彗星、隕石ともぶつかっていました。
人類が百年間かけてまわりの環境をむちゃくちゃにしてしまって、そのまま滅びて行っても、地球は数万年を掛ければきっと元通りにできるのでしょう。地球の年齢から見れば、いままで生きてきた時間の、そうですね、十万分の一ぐらいでしょうか。
環境を破壊して困るのは決して地球ではなく、人類自身です。そして、不幸にして人類と同じ時代を生きているほかの動植物です。
謙虚に自分の弱さを認め、人間が生きていける条件いかに厳しく、いまの環境がいかに有り難いかを、とにかく認識、自覚することが先決かと思いました。
どうすれば種族の生存が長らえるか、自ずと少しずつ答えが見えてくるのではないでしょうか?
慎重に、大事に扱わないと、いまにもガラスが割れて、膜が破れそうです。
はたしてそうでしょうか?
他の動物の毛皮でようやく寒さを凌げ、コンクリートで出来た構造物の中に身を隠す人類は、どこにそんなに巨大なパワーがありましょうか?地震、洪水、強風、大自然の猛威の前に、人類は相変わらず無力で、かよわい存在ではありませんか?
数十億年にもなる地球の年齢のなか、人類の仲間が登場したのはせいぜい数百万年前、まして歴史に残る文明時代は数千年です。
長い長い歳月のなか、地球のほうはいくらでも環境の異変を経験してきました、何回もの氷河時代があったし、もしかして巨大彗星、隕石ともぶつかっていました。
人類が百年間かけてまわりの環境をむちゃくちゃにしてしまって、そのまま滅びて行っても、地球は数万年を掛ければきっと元通りにできるのでしょう。地球の年齢から見れば、いままで生きてきた時間の、そうですね、十万分の一ぐらいでしょうか。
環境を破壊して困るのは決して地球ではなく、人類自身です。そして、不幸にして人類と同じ時代を生きているほかの動植物です。
謙虚に自分の弱さを認め、人間が生きていける条件いかに厳しく、いまの環境がいかに有り難いかを、とにかく認識、自覚することが先決かと思いました。
どうすれば種族の生存が長らえるか、自ずと少しずつ答えが見えてくるのではないでしょうか?
【馬関係の本】「菊とサラブレッド」 (David Shapiro著、ミデアム出版社) ― 2008-05-25 17:03:36
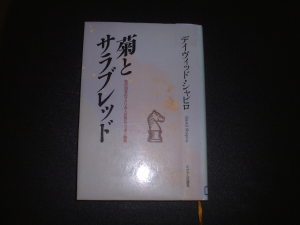
.
1996年の「週刊Gallop」に連載されたコラムに、一部書き下ろしを加えて、10年以上も前に出版された古い本です。
その頃と言えば、まだ現役の?馬キチで、「週刊競馬ブック」はよく読んでいましたが、「週刊Gallop」はごくたまにコンビニで立ち読みした程度でした。先週に図書館で見かけるまでは、寡聞ながら、この本の存在は知らないばかりか、作者についてもほとんど意識したことがありませんでした。
意外に、おもしろかったのであります。
いや、意外にと言ったら失礼です。作者は在日30年のアメリカ人ですが、その日本語は軽妙にして優雅、内容も本当におもしろくて、馬好き、競馬好きは、きっと読んでいて幸せを感じるだろうと思いました。
ダンスインザダークやサクラローレルが走った年の競馬も懐かしいですが、時々出てくるニューヨーク競馬の思い出、そしてなにより、日米の競馬狂たちの姿が、たまらなく愛しく感じます。
そういう人生を選択することも、思えば、できたのですな。
1996年の「週刊Gallop」に連載されたコラムに、一部書き下ろしを加えて、10年以上も前に出版された古い本です。
その頃と言えば、まだ現役の?馬キチで、「週刊競馬ブック」はよく読んでいましたが、「週刊Gallop」はごくたまにコンビニで立ち読みした程度でした。先週に図書館で見かけるまでは、寡聞ながら、この本の存在は知らないばかりか、作者についてもほとんど意識したことがありませんでした。
意外に、おもしろかったのであります。
いや、意外にと言ったら失礼です。作者は在日30年のアメリカ人ですが、その日本語は軽妙にして優雅、内容も本当におもしろくて、馬好き、競馬好きは、きっと読んでいて幸せを感じるだろうと思いました。
ダンスインザダークやサクラローレルが走った年の競馬も懐かしいですが、時々出てくるニューヨーク競馬の思い出、そしてなにより、日米の競馬狂たちの姿が、たまらなく愛しく感じます。
そういう人生を選択することも、思えば、できたのですな。
最近のコメント