【馬関係の本】「人・他界・馬」 (小島瓔禮編著) ― 2007-04-17 07:56:34
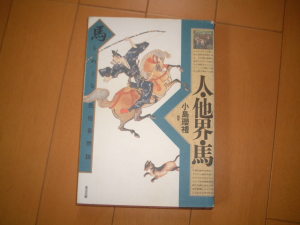
.
こちらは東京美術社より、1991年に発行された本です。
「馬をめぐる民俗自然誌」というサブタイトルもある通り、全書は12の章から成り、いずれも民俗、神話のなかの馬について書かれた話です。
第1章「馬と人生~日本人のみた馬」は、かつての日本で、いかに馬が身近で重要な仲間であったかを説いています。
中部から東北地方あたりの農家は、馬屋は農家の土間続きにあって、芭蕉が「蚤虱馬の尿する枕元」と詠んだように、人馬同居していました。そこで生まれた様々な馬祝い、馬繕いの習俗、そして馬言葉についての研究が書かれています。
第2章「馬頭観音以前のこと~生死観から見た馬の供養」は、馬頭観音から馬の卒婆塔などを語っています。
なかで印象深いなのは、「馬の仕合吉」のなかで柳田国男が「馬の幸福」を論じているくだりです。「死んでは成らないという天だけは、わすかに人間と共通した利害であるが、生かしておいてどうするかというと、天寿をまっとうするまでは、手綱、くつわで駆使するばかりである。」、その文章は馬の不幸は人間が考えなければならない、という文明批判ですが、それだけ馬の存在が身近で大きかった、とも言えます。
第3章「天から子馬で来る女~日本の妖怪信仰からの展望」はダイバ風、ダイバ・ギバの話がメイン、第4章「大王の世紀と馬飼い部~古代史の馬を飼う部民」は馬飼部の話が中心です。
第5章「神々の馬~日本の神信仰とヨーロッパの魔の狩人」、第6章「春を舞う馬~日本の春駒とヨーロッパのひょこすか馬」、第7章「馬と豊饒の女神~日本の大嘗祭とヨーロッパの穀物神信仰」は、いずれも日本での民俗、信仰をヨーロッパと比較しているものです。
なかでもおもしろいのは、徳島県あたり伝わっている「首切れ馬」の話を、ゲルマン人の The wild hunt と対比するところでしょうか。
第8章「魔の馬の足跡~中央アジアの宗教表象からユーラシア」からは、日本を完全に離れ、外国でも馬にまつわる様々な民俗、宗教、伝承の話です。ここで有名な馬頭琴の話も出ています。
第9章「天馬の歌~中国大陸の民俗からの展望」は、中国での話がメインです。汗血馬の話だけではなく、龍馬伝説、「馬王祭」など馬の民俗行事について言及しています。
馬に関する神話伝説は非常に多いですが、特に多くの民俗で見られるテーマとしては、太陽の馬、雷の馬、水の馬が揚げられます。
第10章「馬の起源と太陽の馬~ユーラシアの神話からの展望」は、馬を持たなかったアメリカ原住民たちのなかにも、馬の起源に関する神話が次々と生まれたことから始まり、そして「太陽の馬」など馬の神話伝説を広く論じています。
次の第11章「雷の馬・王殺しの馬~西アジアの神話からユーラシアへ」は、「雷の馬」、「水の馬」などについて書かれています。
最後、第12章「生と死の馬~ヨーロッパの民俗からの展望」はヴォーダン(オーディン)の話など、数多く存在する馬に関するヨーロッパの民話、神話を取り上げ、最後はキリスト教信仰と習合する話まで書かれています。
いずれにして、この1冊で馬に関わる民俗・伝承に触れることができます。人間にとって馬がいかに生活にかかせない重要な存在であったかは再認識でき、馬は歴史を動かし、文化の形成にも大きく影響していると言えます。
こちらは東京美術社より、1991年に発行された本です。
「馬をめぐる民俗自然誌」というサブタイトルもある通り、全書は12の章から成り、いずれも民俗、神話のなかの馬について書かれた話です。
第1章「馬と人生~日本人のみた馬」は、かつての日本で、いかに馬が身近で重要な仲間であったかを説いています。
中部から東北地方あたりの農家は、馬屋は農家の土間続きにあって、芭蕉が「蚤虱馬の尿する枕元」と詠んだように、人馬同居していました。そこで生まれた様々な馬祝い、馬繕いの習俗、そして馬言葉についての研究が書かれています。
第2章「馬頭観音以前のこと~生死観から見た馬の供養」は、馬頭観音から馬の卒婆塔などを語っています。
なかで印象深いなのは、「馬の仕合吉」のなかで柳田国男が「馬の幸福」を論じているくだりです。「死んでは成らないという天だけは、わすかに人間と共通した利害であるが、生かしておいてどうするかというと、天寿をまっとうするまでは、手綱、くつわで駆使するばかりである。」、その文章は馬の不幸は人間が考えなければならない、という文明批判ですが、それだけ馬の存在が身近で大きかった、とも言えます。
第3章「天から子馬で来る女~日本の妖怪信仰からの展望」はダイバ風、ダイバ・ギバの話がメイン、第4章「大王の世紀と馬飼い部~古代史の馬を飼う部民」は馬飼部の話が中心です。
第5章「神々の馬~日本の神信仰とヨーロッパの魔の狩人」、第6章「春を舞う馬~日本の春駒とヨーロッパのひょこすか馬」、第7章「馬と豊饒の女神~日本の大嘗祭とヨーロッパの穀物神信仰」は、いずれも日本での民俗、信仰をヨーロッパと比較しているものです。
なかでもおもしろいのは、徳島県あたり伝わっている「首切れ馬」の話を、ゲルマン人の The wild hunt と対比するところでしょうか。
第8章「魔の馬の足跡~中央アジアの宗教表象からユーラシア」からは、日本を完全に離れ、外国でも馬にまつわる様々な民俗、宗教、伝承の話です。ここで有名な馬頭琴の話も出ています。
第9章「天馬の歌~中国大陸の民俗からの展望」は、中国での話がメインです。汗血馬の話だけではなく、龍馬伝説、「馬王祭」など馬の民俗行事について言及しています。
馬に関する神話伝説は非常に多いですが、特に多くの民俗で見られるテーマとしては、太陽の馬、雷の馬、水の馬が揚げられます。
第10章「馬の起源と太陽の馬~ユーラシアの神話からの展望」は、馬を持たなかったアメリカ原住民たちのなかにも、馬の起源に関する神話が次々と生まれたことから始まり、そして「太陽の馬」など馬の神話伝説を広く論じています。
次の第11章「雷の馬・王殺しの馬~西アジアの神話からユーラシアへ」は、「雷の馬」、「水の馬」などについて書かれています。
最後、第12章「生と死の馬~ヨーロッパの民俗からの展望」はヴォーダン(オーディン)の話など、数多く存在する馬に関するヨーロッパの民話、神話を取り上げ、最後はキリスト教信仰と習合する話まで書かれています。
いずれにして、この1冊で馬に関わる民俗・伝承に触れることができます。人間にとって馬がいかに生活にかかせない重要な存在であったかは再認識でき、馬は歴史を動かし、文化の形成にも大きく影響していると言えます。
最近のコメント