【観戦記】PRIDE無差別級グランプリ2006決勝戦 ― 2006-09-14 13:40:03
日曜日はさいたまスーパーアリーナまで行てきました。
わりと真ん中のいい席ですが、それでも、双眼鏡を忘れたこともあり、グラウンドになるとモニタを見るしかありませんでした。やっぱり、格闘技の会場は、せいぜい横浜文体や代々木第2あたりまでが適切かと思いました。
でも試合内容はとてもエキサイトで、よい大会だと思います。
第1試合: × 西島洋介 vs エヴァンゲリスタ・サイボーグ ○
寝技があまり得意でないと思われたサイボーグ選手が、タックルからテイクダウンを取り、さらに寝技が苦手な西島選手をスリーパーで下しました。鳴り物入りでPRIDEに参戦してきた西島ですが、これで3連敗、パンチ以外の武器も磨かないと、レベルの高いPRIDEでは前途多難でしょう。
第2試合: × ヴァンダレイ・シウバ vs ミルコ・クロコップ ○
トーナメントの準決勝ですので、この日は第2試合から会場内がヒートアップしまくりました。
ミルコはコンディションが良さそうで、積極的な戦い方。シウバのほうも、打撃で劣勢になりながらも一歩も引かず、果敢に打ち合いに挑んだために、激しいいい試合となりました。最後はミルコの妖刀ハイキックが久々に決まり、シウバがくずれ落ちるように倒れてしまいました。
第3試合: × アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ vs ジョシュ・バーネット ○
後ろの席の人が、年間ベストバウト候補と言っていたが、それぐらい両者がかみ合った好試合でした。打撃も互角なら、素晴らしい寝技の攻防も見応え充分です。しかしノゲイラを相手にこれだけ寝技の戦いができる人は、菊田早苗以外では初めてではないでしょうか?
最後は判定で2対1、どちらの手が上がっても不思議がないぐらいの接戦でしたが、会場の空気ではジョシュを支持していたと思います。
第4試合: × セルゲイ・ハリトーノフ vs エメリヤーエンコ・アレキサンダー ○
この試合はトーナメントのリザーブ戦なので、第4試合に組まれました。今後PRIDEヘビー級戦線でトップを張り合う可能性があるふたりは、これが初対決。
勝ったアレキサンダーはこれからポカを注意すれば、チャンピオン争いに加わることが可能だと思います。ハリトーノフも怪我から回復しての初戦、まだコンディションは100%でないと思われるので、次の試合に期待したいです。
第5試合: × イ・テヒョン vs ヒカルド・モラエス ○
これまでの試合があまりに高レベルで熱い戦いだっただけに、観客もこのあたりでちょっと休憩モードに入りました。
イ・テヒョンは完全にスタミナ不足で後半はほとんどスローモーション。モラエスも40歳になって体力が落ちたが、アブソリュートに出ていた頃の印象からはちょっと物足りない、そんな感じでした。
第6試合: ○ 中村和裕 vs 中尾“KISS”芳広 ×
前の試合以上、大きくブーイングを浴びたのがこの第5試合の日本人対決でした。
戦前の煽りとは正反対で、しかしほぼ予想通りの冷めた試合。印象のなか、中尾選手の試合はいつもこのような単調でカウンタねらいの試合運びです。体力は日本人選手のなかでかなり上位に入るものを持ち、レスリングの基本もしっかりできているので、もうちょっと攻めのバリエーションを増やして、積極的な戦い方ができれば、と思いますが。
休憩時間が終わったあと、横浜でのウェルター級トーナメント決勝とライト級タイトルマッチの宣伝で、先日武士道で勝利を収めていた郷野、三崎、五味の3選手がリングにあがりました。ここでも、郷野選手のキャラが目立ち、毒舌も炸裂しました。
第7試合: ○ マウリシオ・ショーグン vs ザ・スネーク ×
ザ・スネークはたぶんMARSかどこかの大会で1回見ただけですが、悪くない選手です。強敵相手でも臆することなく、長いリーチを生かした打撃を繰り出しました。しかし、さすがに復帰戦のショーグンはここでつまずくわけにも行かず、冷静に相手の打撃を捌き、最後は得意のえぐい踏みつけ攻撃で試合を制しました。
第8試合: ○ ヒカルド・アローナ vs アリスター・オーフレイム ×
アローナ選手は結構人気ありますね。戦い方はどちらかというと地味なタイプですが、女性ファンからの支持も多く、会場内の人気は結構高いです。オーフレイム選手はローの受け方がよくなく、怪我をしたような感じでした。
第9試合: ○ ミルコ・クロコップ vs ジョシュ・バーネット ×
いよいよ決勝戦、ミルコは相変わらず調子がよくて、闘牛士のようにジョシュのタックルを切り、強烈なパンチとミドルキックを叩き込みます。ジョシュもよく頑張り、ときおり強烈なローキックもヒットさせたが、この日はミルコの日でした。最後はガードポジションからのパウンドが決まり、1回ぐらいひじが入ったようにも見えますが、それがなくてもミルコの勝ちだったのでしょう。
試合に勝った直後、会場から Happy bearthday!のかけ声が飛び、なんとこの日はミルコの誕生日でもありました。誕生日に念願のチャンピオンとなり、ミルコの目に光るものが見えました。
それにしてもこの日のミルコは鬼神のように強く、年末には、この状態でもう1度エメリヤエンコ・ヒョードルと戦わせてみたいものです。
わりと真ん中のいい席ですが、それでも、双眼鏡を忘れたこともあり、グラウンドになるとモニタを見るしかありませんでした。やっぱり、格闘技の会場は、せいぜい横浜文体や代々木第2あたりまでが適切かと思いました。
でも試合内容はとてもエキサイトで、よい大会だと思います。
第1試合: × 西島洋介 vs エヴァンゲリスタ・サイボーグ ○
寝技があまり得意でないと思われたサイボーグ選手が、タックルからテイクダウンを取り、さらに寝技が苦手な西島選手をスリーパーで下しました。鳴り物入りでPRIDEに参戦してきた西島ですが、これで3連敗、パンチ以外の武器も磨かないと、レベルの高いPRIDEでは前途多難でしょう。
第2試合: × ヴァンダレイ・シウバ vs ミルコ・クロコップ ○
トーナメントの準決勝ですので、この日は第2試合から会場内がヒートアップしまくりました。
ミルコはコンディションが良さそうで、積極的な戦い方。シウバのほうも、打撃で劣勢になりながらも一歩も引かず、果敢に打ち合いに挑んだために、激しいいい試合となりました。最後はミルコの妖刀ハイキックが久々に決まり、シウバがくずれ落ちるように倒れてしまいました。
第3試合: × アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ vs ジョシュ・バーネット ○
後ろの席の人が、年間ベストバウト候補と言っていたが、それぐらい両者がかみ合った好試合でした。打撃も互角なら、素晴らしい寝技の攻防も見応え充分です。しかしノゲイラを相手にこれだけ寝技の戦いができる人は、菊田早苗以外では初めてではないでしょうか?
最後は判定で2対1、どちらの手が上がっても不思議がないぐらいの接戦でしたが、会場の空気ではジョシュを支持していたと思います。
第4試合: × セルゲイ・ハリトーノフ vs エメリヤーエンコ・アレキサンダー ○
この試合はトーナメントのリザーブ戦なので、第4試合に組まれました。今後PRIDEヘビー級戦線でトップを張り合う可能性があるふたりは、これが初対決。
勝ったアレキサンダーはこれからポカを注意すれば、チャンピオン争いに加わることが可能だと思います。ハリトーノフも怪我から回復しての初戦、まだコンディションは100%でないと思われるので、次の試合に期待したいです。
第5試合: × イ・テヒョン vs ヒカルド・モラエス ○
これまでの試合があまりに高レベルで熱い戦いだっただけに、観客もこのあたりでちょっと休憩モードに入りました。
イ・テヒョンは完全にスタミナ不足で後半はほとんどスローモーション。モラエスも40歳になって体力が落ちたが、アブソリュートに出ていた頃の印象からはちょっと物足りない、そんな感じでした。
第6試合: ○ 中村和裕 vs 中尾“KISS”芳広 ×
前の試合以上、大きくブーイングを浴びたのがこの第5試合の日本人対決でした。
戦前の煽りとは正反対で、しかしほぼ予想通りの冷めた試合。印象のなか、中尾選手の試合はいつもこのような単調でカウンタねらいの試合運びです。体力は日本人選手のなかでかなり上位に入るものを持ち、レスリングの基本もしっかりできているので、もうちょっと攻めのバリエーションを増やして、積極的な戦い方ができれば、と思いますが。
休憩時間が終わったあと、横浜でのウェルター級トーナメント決勝とライト級タイトルマッチの宣伝で、先日武士道で勝利を収めていた郷野、三崎、五味の3選手がリングにあがりました。ここでも、郷野選手のキャラが目立ち、毒舌も炸裂しました。
第7試合: ○ マウリシオ・ショーグン vs ザ・スネーク ×
ザ・スネークはたぶんMARSかどこかの大会で1回見ただけですが、悪くない選手です。強敵相手でも臆することなく、長いリーチを生かした打撃を繰り出しました。しかし、さすがに復帰戦のショーグンはここでつまずくわけにも行かず、冷静に相手の打撃を捌き、最後は得意のえぐい踏みつけ攻撃で試合を制しました。
第8試合: ○ ヒカルド・アローナ vs アリスター・オーフレイム ×
アローナ選手は結構人気ありますね。戦い方はどちらかというと地味なタイプですが、女性ファンからの支持も多く、会場内の人気は結構高いです。オーフレイム選手はローの受け方がよくなく、怪我をしたような感じでした。
第9試合: ○ ミルコ・クロコップ vs ジョシュ・バーネット ×
いよいよ決勝戦、ミルコは相変わらず調子がよくて、闘牛士のようにジョシュのタックルを切り、強烈なパンチとミドルキックを叩き込みます。ジョシュもよく頑張り、ときおり強烈なローキックもヒットさせたが、この日はミルコの日でした。最後はガードポジションからのパウンドが決まり、1回ぐらいひじが入ったようにも見えますが、それがなくてもミルコの勝ちだったのでしょう。
試合に勝った直後、会場から Happy bearthday!のかけ声が飛び、なんとこの日はミルコの誕生日でもありました。誕生日に念願のチャンピオンとなり、ミルコの目に光るものが見えました。
それにしてもこの日のミルコは鬼神のように強く、年末には、この状態でもう1度エメリヤエンコ・ヒョードルと戦わせてみたいものです。
【蔵書自慢】Complete Science of WRESTLING ― 2006-09-14 20:58:02
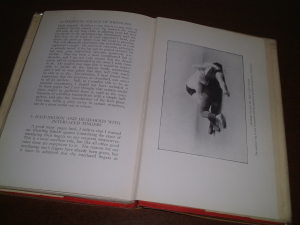
.
先日のPRIDEでも大活躍したジョシュ・バーネット選手が、インタビューでキャッチ・レスリングを語ったことで、久々にキャッチが脚光を浴びている感じです。
いまのレスリング(アマレス)は、グレコ・ローマン・スタイルとフリー・スタイルの2種類に分かれていますが、フリースタイルという名前になったのは、たぶん1948年のロンドン・オリンピックあたりで、それまではオリンピックでもキャッチ・アズ・キャッチ・キャン・スタイル(Catch-As-Catch-Can Style)と呼ばれていました。
19世紀末から20世紀初頭あたりは、前にも書いたことがありますが、ある意味でプロレスの黄金時代とも言える時期でした。そして、そのガス灯時代のキャッチ・レスリングの教科書とも言うべきなのが、題記の書物ではないかと思います。
「Complete Science of WRESTLING」は、ロンドンのAthletic Publications Limited から 出版された本で、作者はその時代で最も偉大なプロレスラーのひとり、George Hackenschmidt(ジョージ・ハッケンシュミット)です。
僕は十年前ぐらい、神保町の古本屋で入手したのですが、つい最近、出版年代は1909年だとわかったばかりです。
内容は、3つの章に分かれています。本人が出演している写真をふんだんに使って、ひとつひとつの技、ムーブを詳しく解説しています。
Chapter I . A Wrestler's Training
Chapter II . Up-standing Wrestling and Standing Throws
Chapter III . Ground Wrestling
それと、興味深いなのは、Ju-jutsuという単語が何回か出ています。
例えば、第1章には、柔術のトレーニングがキャッチ・レスリングにも有効だとしている文章があります。
Similarly will they find practice at Ju-jutsu, especially with a Japanese instructor, extremely useful. The presence of the jacket and consequent difference in the method of coming to grips with an opponent, and the totally different idea of the style, may provide arguments against the claim that the Japanese style possesses any particular utility for the cacth-as-catch-can wrestler, but he will find that the increased knowledge of tripping he will gain, and, above all the practice of the art of balance, which is the very essence of Ju-jutsu, will be of inestimable value to him.
ジョシュの語るキャッチと必ずしも一致しないかも知れませんが、少なくともHackenschmidtは、いまからほぼ百年前、すでに柔術に対する認知がかなりあったと伺えます。
先日のPRIDEでも大活躍したジョシュ・バーネット選手が、インタビューでキャッチ・レスリングを語ったことで、久々にキャッチが脚光を浴びている感じです。
いまのレスリング(アマレス)は、グレコ・ローマン・スタイルとフリー・スタイルの2種類に分かれていますが、フリースタイルという名前になったのは、たぶん1948年のロンドン・オリンピックあたりで、それまではオリンピックでもキャッチ・アズ・キャッチ・キャン・スタイル(Catch-As-Catch-Can Style)と呼ばれていました。
19世紀末から20世紀初頭あたりは、前にも書いたことがありますが、ある意味でプロレスの黄金時代とも言える時期でした。そして、そのガス灯時代のキャッチ・レスリングの教科書とも言うべきなのが、題記の書物ではないかと思います。
「Complete Science of WRESTLING」は、ロンドンのAthletic Publications Limited から 出版された本で、作者はその時代で最も偉大なプロレスラーのひとり、George Hackenschmidt(ジョージ・ハッケンシュミット)です。
僕は十年前ぐらい、神保町の古本屋で入手したのですが、つい最近、出版年代は1909年だとわかったばかりです。
内容は、3つの章に分かれています。本人が出演している写真をふんだんに使って、ひとつひとつの技、ムーブを詳しく解説しています。
Chapter I . A Wrestler's Training
Chapter II . Up-standing Wrestling and Standing Throws
Chapter III . Ground Wrestling
それと、興味深いなのは、Ju-jutsuという単語が何回か出ています。
例えば、第1章には、柔術のトレーニングがキャッチ・レスリングにも有効だとしている文章があります。
Similarly will they find practice at Ju-jutsu, especially with a Japanese instructor, extremely useful. The presence of the jacket and consequent difference in the method of coming to grips with an opponent, and the totally different idea of the style, may provide arguments against the claim that the Japanese style possesses any particular utility for the cacth-as-catch-can wrestler, but he will find that the increased knowledge of tripping he will gain, and, above all the practice of the art of balance, which is the very essence of Ju-jutsu, will be of inestimable value to him.
ジョシュの語るキャッチと必ずしも一致しないかも知れませんが、少なくともHackenschmidtは、いまからほぼ百年前、すでに柔術に対する認知がかなりあったと伺えます。
最近のコメント